今回の実例は、少し前のものだが、報道記事から。というより、報道記事に引用符つきで(発言そのままで)引用されている当局者の発言から。
この10月下旬、米国ニューメキシコ州で映画撮影中に起きた、小道具の銃による痛ましい事故で、カメラの後ろにいた撮影監督が亡くなり、そのそばにいた監督も負傷するということがあったのは、日本語圏のメディアでもそこそこ大きく報じられている通りである。
事故が起きたのは、ジョエル・ソウザ監督による映画『Rust』(原題)の撮影現場で、プロデューサーで主演の俳優アレック・ボールドウィンが小道具として手渡された銃が、何らかの理由で撮影用の空砲の類ではなく実弾が入っており、そのため、発砲シーンを撮影したときに本当に銃弾を発射することになってしまい、カメラの後ろにいたハリナ・ハッチンス撮影監督が死亡、ソウザ監督も負傷した。10月21日の出来事である。
このときに何が起きたのか、なぜそのようなことになったのかについては、現在も捜査が進められている(ので「誰が悪い」といった結論的なものはまだ出ていない)が、こういう事故が起きてしまった環境・状況についての解説記事もずいぶん出ていた。英語だけでなく日本語でも書かれている。例えばEiga.comの下記記事(小西未来さんによる)は、映画撮影現場のいわゆる「ブラック労働」ぶりを具体的に説明してくれている。
特に『Rust』の現場はひどくて、事故の直前にもカメラクルーがやめてしまっていたという。やりきれないのは、亡くなったハッチンス撮影監督がその「ブラック労働」の環境改善を求めて活動していた映画人のひとりだったということだ。
Halyna Hutchins should be trending number one on Twitter, not Alec Baldwin.
— StandForBetter.org (@StandForBetter) 2021年10月22日
As a union sister in the Cinematographer's Guild, .@ICGLocal600, her death on the set of Rust reminds us that safety in the workplace is a basic human right. Period.#RIPHalynaHutchins #IASolidarity pic.twitter.com/jreIDXER7V
前置きはこのくらいにして、本題に入ろう。今回の実例は、事故発生から数日後、警察の調べがある程度進んで、捜査責任者が記者会見を行ったときのBBCの報道記事から。記事はこちら:
この記事で、引用符を使って引用されている警察官の発言から:

キャプチャ画像内の最後のパラグラフ:
"I think the facts are clear - a weapon was handed to Mr Baldwin. The weapon [was] functional and fired a live round killing Ms Hutchins and injuring Mr Souza," he said about the killing.
太字で示した部分に注目してもらいたい。
《不定冠詞》のaと、《定冠詞》のtheについて、「初出箇所はaで、二度目からはthe」といったように説明されることが多いと思うが、これはまさにその通りの実例だ。最初の "a weapon" は「ある武器」「武器がひとつ」で、「武器」が初出の箇所。そのあとに続く "The weapon" は、「その武器」で、つい先ほど言及した「武器」のことを言っている。「ボールドウィン氏にある武器が手渡された。その武器は機能する武器で、実弾を発射した」という構造を、不定冠詞と定冠詞が作っているわけである。
定冠詞と不定冠詞に関して、実際の報道記事などで(ここでは記者会見を行った警察官の発言の引用だが)、ここまで見事に文法解説書通りになっている例を見ることはかなり珍しい。
珍しいので、メモらずにはいられなかったのである。
なお、"The weapon [was] functional ..." とブラケット(角カッコ)が用いられているのは、ここに記されている警察官の発言そのものではwasは発話されていなかったとか別の語(isとかwereとか)だったという場合に、記事を書いた人が文法・語法的に判断して正しい(標準的な)形になるよう修正・補足を行った、という印である。これは学術論文などを書く際にも用いられるルールで、何かを引用する際、引用元では欠けている単語を補って意味がすっと通るようにする、というような場合に見られる。
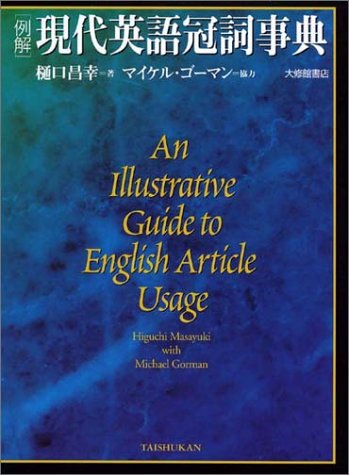
![英語の冠詞がわかる本[改訂版] 英語の冠詞がわかる本[改訂版]](https://m.media-amazon.com/images/I/41RVbKf3-YL._SL500_.jpg)
