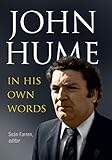このエントリは、2020年8月にアップしたものの再掲である。
-----------------
ジョン・ヒュームが亡くなった。この人がいなかったら、北アイルランドは今でもドンパチが続いていたかもしれない。そういう存在だ。
この人については、ここではなく本家のブログで書くべきだと思うのでここでは深入りしない。20世紀後半の経験と知恵を体現するような存在だった。
いつか、というか近いうちにこのニュースに接する日が来ると、もう何年も前から分かってはいたのだが、まさかこんな、人が集まることができず、お見送りも満足にできないときに逝ってしまうなんて、悲しすぎる。人と人を、人々と人々をつないだ人なのに。
今回の実例は、訃報が流れたあと、多くの人々がツイートしている故人の言葉から。
“ireland is not a romantic dream; it is not a flag; it is 4.5m people divided into two powerful traditions. the solution will be found not on the basis of victory for either, but on the basis of agreement and a partnership between both”
— Anna Cafolla (@AnnaCafolla) 2020年8月3日
📷 john hume at a demo in derry, 1969 pic.twitter.com/X0kIb4vNUn
「アイルランドはロマンチックな夢ではない」というのは、アイルランドを「ロマンチックな夢」扱いする人々が世界中に大勢いたことを示している。その「夢」はナショナリスティックな夢、「ネイション」というものを「物理的な力 physical force」で、つまり武力で勝ち取ろうとする夢で、19世紀から20世紀に、主にアイルランド島の外にいるアイリッシュの人々(アイリッシュ・ディアスポラ)の間で好まれ、憧憬の対象となり、支持された夢である。その「夢」は、アイルランド島の中では広く共有されてはいなかった。アイルランド島ではもっと現実的な、「革命に殉じる」みたいな甘美な夢ではなくもっと現実的な、今日を生き、明日を行き、子供たちによりよい明日を受け継いでいくという希望とヴィジョンが求められていた。
ジョン・ヒュームは「甘美な夢」の側ではなく、「現実的な希望とヴィジョン」の側にいた人で、そのことを彼自身のこの言葉はとてもよく表している。
以下、原文では略式で全部小文字で書かれているものを、引用にあたって普通の書き方に改める。
Ireland is not a romantic dream; it is not a flag; it is 4.5m people divided into two powerful traditions.
この文の第一文で用いられている《セミコロン (;)》は、「コンマ以上、ピリオド未満」という感じの句読点で、独立した文をandやbutなどの等位接続詞を使わずに結ぶときに用いられる。だから便宜上、読むときは、ピリオドに置き換えて考えてもいいし、", and" など等位接続詞に置き換えて考えてもよい。
文意は「アイルランドはロマンティックな夢ではない。1枚の旗でもない。2つの強力な伝統に分かたれた、450万人の人々である」。
つまりアイルランドは「理想」や「概念」の類ではなく、現実に、家族や友人たちとともに、今日や明日を生きる450万人という人々である、という主張だ。
その「2つの強力な伝統」――「ユニオニスト」と「ナショナリスト」、「プロテスタント」と「カトリック」――が敵対し合い、前者が後者を抑圧するという構造で、北アイルランド紛争は生じ、維持されてきた。
ヒュームはこの紛争を終わりにしようとした。本気でそれに取り組んだ。
The solution will be found not on the basis of victory for either, but on the basis of agreement and a partnership between both.
ここでは《not A but B》「AではなくB」の構造が使われている。
文頭から読み下していけば、意味を取るのは難しくないだろう。
「解決策は見つかるだろう」+「どちらかの側の勝利という基礎の上にではなく」+「双方の間での合意と協力という基礎の上に」。
まさにこの「合意と協力 agreement and partnership」の人であった。
そのために自身の政党内での合意をはかるところから、ヒュームは闘ってきた。ヒュームはナショナリストの政治家だが、「ユニオニストvsナショナリスト」という構図の中で、「対ユニオニスト」以前に「ナショナリスト内部」での合意をはかり、それ以前に、ナショナリストの中でも暴力を絶対に認めないという立場の自分たちの党(SDLP)の中で、暴力によって目的を達成しようとする党(シン・フェイン)と話をするということについての合意をはからねばならなかった。それはとても難しいことだったが、ヒュームはやり遂げた。そしてそれが、現在に続く北アイルランド和平プロセスの始まりとなった。
https://t.co/fWJe2Dfzeb 偉人ジョン・ヒューム死す。こちら、2017年のドキュメンタリーのトレイラー。
— n o f r i l l s /共訳書『アメリカ侵略全史』作品社 (@nofrills) 2020年8月3日
https://t.co/sgpUYIlkgY We Shall Overcome: The Civil Rights Movement in Northern Ireland 1968 - 1969 アイヴァン・クーパーが昨年亡くなって、今年はシェイマス・マロンが逝き、そしてジョン・ヒュームまでも。
— n o f r i l l s /共訳書『アメリカ侵略全史』作品社 (@nofrills) 2020年8月3日
https://t.co/cOe10RNBpw 暴力的紛争の中で、「平和/和平のためには敵と話をしなければならない」という哲学を政治の現場に持ち込んだ人。「敵」はIRAだった。ユニオニストと話をしたことよりシン・フェインと話をしたことのほうが大きい。SDLP党内の反対論をねじふせるのは並大抵のことではなかった
— n o f r i l l s /共訳書『アメリカ侵略全史』作品社 (@nofrills) 2020年8月4日
Gerry Adams pays tribute to 'giant of Irish politics' John Hume following his sad passing. Ar dheis Dé go raibh a anam dílis. #JohnHume @GerryAdamsSF pic.twitter.com/3GAjmZACvj
— Sinn Féin (@sinnfeinireland) 2020年8月3日
https://t.co/THplT2Bknk アダムズが "tsunami of abuse" と言っているのは、SDLP党内からのアダムズ・ヒューム会談に対する反対論のこと。プライベートな形ではその前から接触はあったというあたりも、アレック・リード神父の仲立ちでアダムズ・ヒューム会談が実現したということも。
— n o f r i l l s /共訳書『アメリカ侵略全史』作品社 (@nofrills) 2020年8月4日

John Hume in America: From Derry to DC (English Edition)
- 作者:Fitzpatrick, Maurice,Mitchell, George
- 発売日: 2017/11/30
- メディア: Kindle版