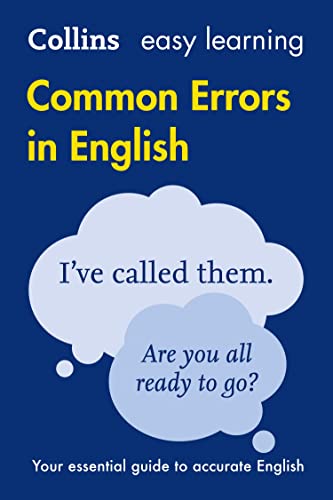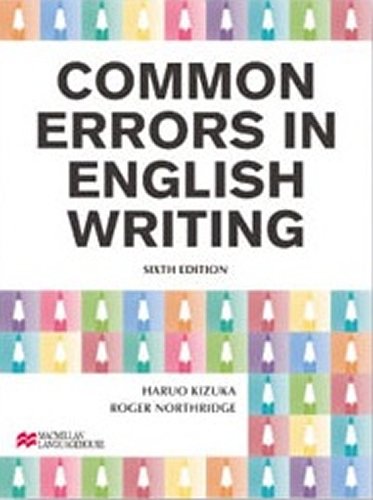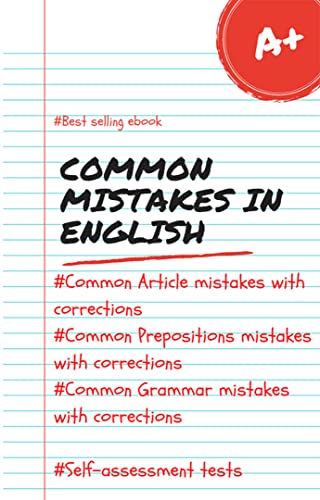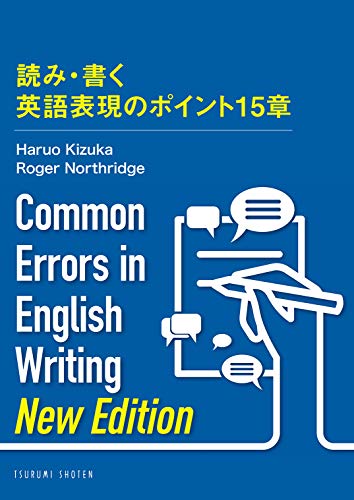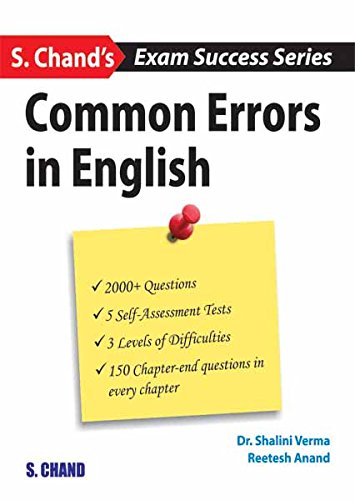今回の実例は、報道記事から。
少し前になるのだが、次のような用例を見かけてメモっていた。出典はBBC Newsのこの記事である。
同じ記事から、文法警察がとんでくるやつ。#英語 #実例
— nofrills/文法を大切にして翻訳した共訳書『アメリカ侵略全史』作品社など (@nofrills) 2022年11月6日
このThere'sは、ここ10年ほどで、ほんとに見ることが増えた。 pic.twitter.com/KeMy7TvnFH
おわかりだろうか。
「文法警察」は英語圏でいうgrammar policeの直訳で、ちょっとした文法ミスでも見逃さずに飛んでくる人々のことを面白おかしくいう。15年前は「文法ナチ (grammar Nazis)」という表現が定番だったが、最近その用法は鳴りを潜めた。
「文法警察」は、Twitterにもそう名乗っているアカウントがいくつもあるが(中の人は何らかの分野の言語学者だったりすることが多い。つまり「間違いのサンプル探し」に余念のない人々だ)、うちらのような外国人(「外国語としての英語」を使う、または使おうと頑張る人々)のミスに目を光らせるというよりは、英語母語話者のやりがちな間違いを指摘して回っている。日本語でいえば、「はてなブログとゆうサービス」や「はてなブログと言うサービス」という記述を見つけては「『~という』ですね」と指摘したり、「アボガド料理専門店」と書いている人を見つけては「アボカドですよ」とリプしたり、という感じだ。
ここで私が「文法警察がとんでくる」と言っている記述は:
There's a lot of people
そう、これは、a lot of peopleという複数形に合わせなければならないので、本来は There are a lot of people と書く/言うべきなのである。
しかし実際には、There isとかThere areとはっきり2語で発話することはとても少なくて、There'sとつい口をついて出るということがとても多いそうだ。しかもこれは、学のない人に限らない。その点、日本語の「そうゆうこと」(規範的には「そういうこと」)といった表記ともちょっと層が違っているかもしれない。
上記の例での発言者、Brandon Borrman氏も、Twitterでかつてグローバル・コミュニケーション部門のトップを務めていた方なのだかr、決して学のない層ではないだろう。
それでも、口頭ではどうしても There are と言う代わりに There's と言ってしまうようだ。
なお、口頭での発言でなく、文章を書くときは、自分でもこういうところは気を付けるだろうし、自分が気づかなくても校正の段階で指摘が入るはずである。
今回は短いけどここまで。
このような例は「ネイティブがやりがちな文法ミス」としてネット上にもまとまっている。Common errors in Englishといった語句で検索するとよい。
※1234字(なんかうれしい)。今回は出典としている記事を読む必要はないので、内容的な解説はしない。
サムネ: