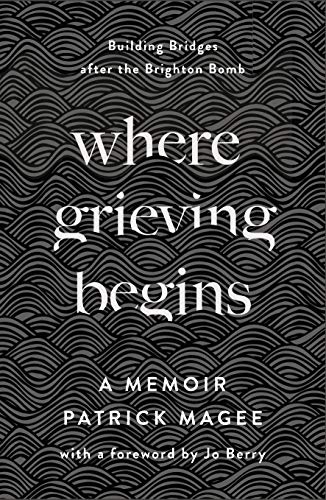Twitter/Xの画面を見たら、Helldiversという単語がTrendsに入っていた。どんなに低気圧でだるくても眠くても、知らない単語があればチェックしてみるのが習性である。字面から漫画か何かか、あるいはガザでアメリカがやってる食糧支援に偽装したデス・トラップ、GHFに参加している面々のことか(GHFには反イスラムの暴力的バイカー集団が参加していることが伝えられている)、と当たりをつけてみてみたら、ゲームのようだ。
時は西暦2084年。宇宙に進出した人類は、さまざまなエイリアンの襲撃を受け、窮地に立たされていた。プレイヤーは、そんな人類の脅威を取り除くために戦う精鋭・特殊部隊“HELLDIVERS(ヘルダイバー)”の一員となり、エイリアンたちと激闘を繰り広げていくことになる。
本作は、一筋縄ではいかない挑戦的なバトルを楽しめる“超骨太”のシューティング。限られた弾薬数、救援が到着するまでの残り時間、無限かと感じられるほどに次々と迫り来るエイリアンたち——。緊張感あふれる戦場では、正確でいて時に大胆なアクションや戦術、そして仲間との連携が重要となる。……
なぜこの単語がTrendsに入っているかを見てみれば、例えば「新作がアナウンスされた」とか「映画化が決定した」といったゲーム系のニュースがあったからではない。「ターニング・ポイント」という極右デマのムーヴメントを組織化したチャーリーなんとか(関心がなさすぎて名前を憶えていない)を撃ち殺した人物が使ってた暗号みたいなのが、このゲームで使われるコードだったということが判明して、メインストリーム・メディアが流していた「アンティファの犯行」とかいったデマ・誤情報が覆されたのだそうだ。
何でも、銃弾のケーシングに彫り込まれていた下向きの矢印3本が並んでいるのが「アンティファのシンボル」として取りざたされていたが*1、それは実はこのHelldiversというゲームで使われるコードで、「下向き矢印3本」だけでなく、「上向き矢印1本、右向き矢印1本、下向き矢印3本」というのがセットになっていて、 そっから「下向き矢印3本」だけを切り出すのは、それなんて国家安康、って感じだな。ちなみにこのコードを使うと Eagle 500kg Bombってのが出てくるんだって。ミームにもなってるんだって。私はゲームをやらないので文字でしか知らないんだけど、「コナミコマンド」みたいなものかな。
People are interpreting the “three arrows” as an “antifa symbol” but it’s described as:
— Elai (@elaifresh) 2025年9月12日
Up arrow, right arrow, three down arrows
This is the input for the 500kg bomb in the video game Helldivers II, which is a meme in its own right. Totally apolitical https://t.co/lZ1VKrjkho pic.twitter.com/PJQHUcqOxH
"one of the bullets was engraved with up symbol, right symbol, and 3 down symbols"
— 🏴☠️Nasdorachi🏴☠️ (@Nasdorachi) 2025年9月12日
so the assassin Tyler put the 500KG bomb Helldivers input on one one of his rounds. https://t.co/B3gvcXnLZh pic.twitter.com/8Ek24VBsBU
This is going to expose me as a gamer but both the arrows and the fascist reference they mention for the shooters ammo are direct references to the video game Helldivers 2 and are common memes.
— Zaid Jilani (@ZaidJilani) 2025年9月12日
Casings from Tyler Robinson, Charlie Kirk’s alleged shooter, read “Hey, fascist! Catch! ↑ → ↓↓↓”. The code references the Eagle 500kg Bomb stratagem from Helldivers II, which became a viral meme tied to a powerful airstrike ability in the game. pic.twitter.com/H0ElGrHzGi
— Know Your Meme (@knowyourmeme) 2025年9月12日
Know Your Memeまで出てきてるし…… (^^;)
メインストリーム・メディアは、これを「アンティファだー」とか「トランスジェンダーだー」と大騒ぎしていたらしい。こっぱずかしい。ちなみに、Helldiversというゲームはantifaとは逆の側にいる人たち(つまりfa, もっとちゃんと書けばfash)の間で人気なのだそうだ。
The Internet: "Lol, a Helldivers 2 reference"
— Rebecca 🏳️⚧️ (@CptMidlands) 2025年9月12日
The BBC: "This is directly linked to Antifa and Trans Activism" pic.twitter.com/2P2XNhV8zz
The arrows on the round are nothing to do with any trans stuff btw.
— Mark NBA is dead to me (@iwasmmueller88) 2025年9月12日
It’s a Helldivers 2 reference it would seem. pic.twitter.com/zgnYBLGX4y
Wrong interpretations here, too. Old people shouldn’t be in charge of communicating internet lingo of young folks.
— 🇨🇦 JL 🇨🇦 (@Jose1Pino) 2025年9月12日
The notices bulges is internet lingo for transvestigating someone. The arrows are a code in Helldivers video game.
The anti fascist one is just 3 diagonal arrows https://t.co/JwNpHDgu3U
銃撃容疑者はほかにもいろいろミーム的なものをちりばめているそうで、それらをまとめてくれているスレッドが下記。
1/10
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 2025年9月12日
So the fake claims of "trans" and "antifa" symbols comes from both ammo stamps and casing inscriptions wrongly reported.
They try to paint Tyler as left, but like Crooks this is a fringe right wing Groyper.
Here's the details on registered Republican, Tyler Robinson: https://t.co/bmbF6WVE2c pic.twitter.com/8xeGGMDTzA
"Groyper" ってのがもうわかんないよね。でも私にはどうでもいいから「何かわかんないけどそういう極右フリンジ」とだけ認識して先に行く。いずれにせよ、「アンティファ」でも「トランス」でもない。「サヨク」ではない。
2/10
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 2025年9月12日
The casings read:
-Notices bulges OWO what's this?"
An old meme that started from Tumblr and is now frequently made fun of in alt-right groups like Groypers when "transvestigating" pic.twitter.com/VOwsdAjsEM
"transvestigating" ってのがわかんないよね。でもどうでもいい。字面からだいたいわかるし。
3/10
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 2025年9月12日
Second casing read:
-Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao Ciao Ciao
A song popularized during WWII as part of the anti-fascists movement in Italy.
The heavily catholic alt-right Gyopers have used this song when mocking left activists but also pic.twitter.com/dQ2geupsm5
アメリカでは、極右が歴史的にアンティファが使っていたものを使うということも平気で起きるんだな。ばかばかしい。まともに取り合ってられるか。
4/10
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 2025年9月12日
Individuals like Fuentes have called Charlie Kirk a "liberal in disguise" "a globalist" "a fascist" and a "fake conservative.
This matches with the third casing reading:
"Catch this fascist"
これは過激派あるある。いわゆる「内ゲバ」。Fuentesってのはニック・フエンテスでしょ、この文脈で名前くらいは知ってるような気がするけどそれだけ。調べるのは私にとっては時間の無駄。
5/10
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 2025年9月12日
The last casing read:
"If you are reading this you are gay, lmaoooo"
Part of the deeply homophobic anti-lgbtq culture of groups like Groypers. pic.twitter.com/sc0XEOmrhp
下品で幼稚。
アダムさんのスレッドを単に貼ってるだけなんだけど飽きてきたので、あとはThreadreaderに投げとこう。
@n0fr1ll5 Halo! here is your unroll: https://t.co/6nfMzKxLyL Share this if you think it's interesting. 🤖
— Thread Reader App (@threadreaderapp) 2025年9月12日
ここに列挙されている、銃撃犯の銃弾に彫り込まれていたという文言のように、読んだときに意味が取れないものは、現代の文では、ほぼ例外なく、特定の界隈だけで通用するようなネットスラングやミームである。そのまま英語から日本語にしたって意味が取れないばかりか意味がない。警察の人やBBCのような大手メディアの記者だって、その界隈に通じていなければわからないだろう。
しかし、やっぱり笑いものであることに変わりはない。
msm not recognizing a helldivers reference and blaming antifa is really just chefs kiss pic.twitter.com/tZTzJqqFh3
— Denims (@DenimsTV) 2025年9月12日
"chefs kiss" というのは、ちゃんと書くとchef's kissなのだが(アポストロフィー)、作った料理を味見したシェフが「最高!」というときに手の親指と人差し指でやるしぐさのことで、意味は「最高」。「メインストリームメディア(MSM)がゲームのヘルダイバーへの言及を認識せず、アンティファが悪いと言っているのは、本当にもう最高だ」といった文意。
I still can’t believe the WSJ published that the bullet casings had “transgender ideology” and it turned out to be a fucking HELLDIVERS REFERENCE
— Armand Domalewski (@ArmandDoma) 2025年9月12日
WSJがどうたらというのは、さっきはてブで見たんだけど、これですね。
【ワシントン共同】米国の保守系政治活動家チャーリー・カーク氏(31)が射殺された事件で、ウォールストリート・ジャーナル紙は11日、捜査当局が犯行に使われたとみられるライフルを発見し、内部からトランスジェンダーの権利擁護や反ファシズムを訴える刻印のある弾が見つかったと報じた。ただその後、記事を修正し、一部の当局者からこの分析に懐疑的な見方も出たと伝えた。
ここでアレックス・ガーランドの映画『シヴィル・ウォー』を思わずにはいられない。私が見た日本語字幕は「アンティファによる虐殺」と、まったく反対の方向に転がっていくような誤訳をしていたが(翻訳をした人がそういう思想なんだろうなという質の誤訳)、あの映画の中の大統領は何でもかんでも「アンティファがー」と言うタイプの人間で、アンティファを虐殺したあとの世界があの映画の舞台だ。あの映画が始まる前に起きたことは、たぶん、『アクト・オブ・キリング』みたいなことだ。アメリカがどうなるのかはわからないが、『シヴィル・ウォー』の世界にいたる道は、もう整備されているんだろうと思う。ガザ・ジェノサイドの扱いを見ていても。
*1:「アンティファのシンボル」とは、ひょっとして左斜め下を向いてるやつのことかな……銃撃犯が使ってる真下向いたのとは違うじゃん。アメリカって紋章学的なことやってる人っていないの?
![シビル・ウォー アメリカ最後の日 通常版 [Blu-ray] シビル・ウォー アメリカ最後の日 通常版 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41F-PaktUDL._SL500_.jpg)
![アクト・オブ・キリング オリジナル全長版 2枚組(本編1枚+特典DVD) 日本語字幕付き [Blu-ray] アクト・オブ・キリング オリジナル全長版 2枚組(本編1枚+特典DVD) 日本語字幕付き [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51ciw-HOi2L._SL500_.jpg)